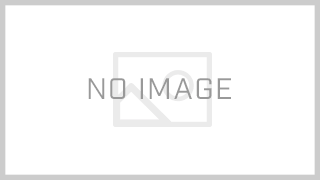やりたいことはある。でも集中できない。そんな私が読んでよかったと思えた一冊。
はじめに
やりたいことはたくさんあるのに、なかなか手がつけられない。本当に作業が進まないんです。
締め切りがあるものはギリギリでなんとかこなすけれど、自分で設定した締め切りなんて、無いも同然。論文執筆やブログの更新も、ずっと「やりたい」と思いながら進まずにいました。
「もっと没頭できるようになりたい」――そんな思いから、この本を手に取りました。
ちなみに、『SINGLE TASK 一点集中術』なども読んでいて、マルチタスクは避けるようにしているのですが……それでも、どうしても集中が続かないのです。
本の概要
著者は鈴木祐氏。「パレオな男」で有名な方ですね。
メンタリストのDaiGoさんが尊敬する方だそうです。
そんな鈴木氏は1日で15本ほどの論文と3冊の本を読み、2~4万字の原稿を書くと前書きに書かれております。スゴイ集中力ですよね。
集中力とはなんぞやというところに始まり、集中力を上げ、維持するための方法が書かれております。
本の紹介
実際に読んでみて、「集中力って、思っていたよりもずっと複雑なスキルなんだな」と感じました。
本書によると、集中力とは次のようなスキルの複合体なのだそうです:
- 自己効力感
- モチベーション管理能力
- 注意の持続力
- セルフコントロール力
つまり、集中するためには「気合い」だけでなく、自分の心理状態や環境との向き合い方が重要だということです。
本書では、集中力を高めるための具体的なテクニックもいくつか紹介されています。
たとえば、「気を散らす要因をあらかじめ取り除く」「脳が活性化するタイミングで作業する」「あえて『小さな不快』を取り入れる」など。どれも最新の科学的知見をベースにしており、実践的です。
他の作業効率向上系の書籍にも記されている内容ではありますが、本書ではより科学的・実践的な視点から語られており、新たな発見がありました。
気付き
この本から得られた気づきは次の3つです。
「習慣化」に繋がること、関連していることがたくさんある
習慣化のテクニックとして「if-thenルール」が有名ですが、本書で挙げられているテクニックとして「儀式を行う」っていうのがあるんですね。集中する作業の前の儀式をするっていう。
この行動をしたら作業に集中するってことでしょうね。
あとは、「できそうなこと」から着手するっていうようなものもありました。
これも習慣化のテクニックと似てるなと。
集中力を維持するには脳の特性を知ってコントロールする必要がある
「意志力」って言葉をよく聞くと思うのですが。
集中したい時に別の誘惑に負ける時って「意志力ないなー」って思いますよね。
本書では意志力の低下は感情コントロールの問題として捉えられると書かれておりました。というか、私はそう理解しました。じゃあ、瞑想とかで、感情コントロールできるようにしていこうかなって思ったり。
こういう感じで脳の特性を知ってコントロールすればめっちゃ没頭できるのかなって思います。
カフェイン摂取のタイミングって大切
とりあえず、「カフェインは最強」ってことらしいです。
カフェイン摂取のタイミングについては色々言われることもありますが、とりあえず、本書でも「起床後90分は摂取しない方がいい」ってことが述べられてました。
私のTo Do
ゴール設定とタスクの細分化をして「これならできそう」レベルまで落とし込む
結局、私のやりたいことは漠然としてて「できそう」レベルまで日々のタスクを細分化できてないなって思ったんですね。で、本書で紹介されてた「報酬感覚プランニング」っていうのを実践してみようかなと。
「小さな不快」で脳を刺激するために、お菓子をやめてみる
日々の「小さな不快」で脳が鍛えられるらしいんですね。お菓子は食べないようにしてるんですが、誘惑に負けて買ってしまうことがあるんです。
でも、誘惑に負けそうになったら「これをやめたら集中力がアップする」って思えばやめられるかも。
とりあえずやってみます。
できるなら、一石二鳥です。
自分に最適なカフェイン摂取のタイミングを調べてみる
集中力upのためのタイミングがあるらしいので、自分の生活リズムも考慮しながら最適なタイミングを見つけて実践してみたいなって思いました。
この本がおすすめな人
- ・やりたいことがたくさんあるけど、どうしても一つの作業に集中できないという人
- ・生徒や学生が授業に集中してくれなくて困ってる先生
まとめ
この本を読んで、「集中力は取り戻せる」とわかってホッとしました。
集中力は、技術であり習慣。ちょっとした工夫で誰でも改善できるものだと感じられたのが最大の収穫です。
タスクが進まず悩んでいる人、自分を責めがちな人にこそ、読んでほしい一冊です。